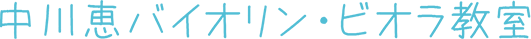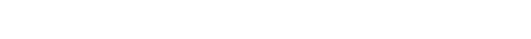初夏の畑と果樹
2020/05/14

京都府井手町の庭のよどみをよくするため、地中の空気と水が流れやすいようにしたのが、標題の写真です。土中の水や空気が動くよう溝を掘り、枝葉や炭を軽く入れます。
雨のあと見にいったら、汚水のような臭いがしました。枝葉や竹や炭をどけてみると、地中から上空へ臭気がぬけていってるようでした。
離れの植えこみの空きスペースに、好きなものを植えていいと大家さんの許可をもらいました。
果樹、冬に陽があたるよう落がおち、でっかくならないもの。
すもも、いちじく、ブルーベリー、ナツグミ、スダチ。
スダチだけ常緑樹で、鉢植えにします。
在来種で小ぶりの品種を選びました。
そのほうがおいしいし、きっと病害虫にも強いでしょう。
落葉樹の植えつけ適期は冬。
これから植えるのに適さない春→夏になるため、苗木をみつけるのに苦労しました。
2月末に届きましたが、根ばりがイマイチ。
野菜もそうですが、地上部からはなかなか分からないものですね。
1ヶ月ほど変化がなくて根づいたのかヤキモキしましたが、暖かくなると葉が出てきました。

アサツキ
3月から木津川市の畑の作業を再開しました。
11月に種まきし越冬したエンドウ、これからぐんぐん伸びてくるため大急ぎで支柱を立てます。
支柱は12月に、京田辺は大住の竹林から切ってきた孟宗竹の枝です。
ネギ、玉ネギは雑草に負けやすいので、埋もれないよう草刈り。
じゃがいもを植え、ニラは株分けして植えなおし。
地中にはツクシがいて、ノビル、アサツキ、イチゴも元気です。

定植後のレタス

定植後のトマト
家から駅まで徒歩5分になったので、夏野菜はポット苗にしました。
レタス、トマト、ナス、黄マクワウリ、スイカ。
どの種も自家採取したものです。
直まきだと気温的に4月後半からでないと まけないのですが、ポットなら3月から作れます。
水の管理ができて、毎日ながめられるのがいいところですが、日々その成長ぶりにヤキモキします。
結局あまり大きくならないうちに暖かくなり、4月下旬に畑へ。
ポットから出したら、根がうずを巻いていてビックリしました。
肥料をあげると根をのばすのをサボるけど、肥料をあげないと地上部の成長を後回しにして根を伸ばすんですね。
根がまっすぐ下へのびる大根と人参は、ポットは向かないので、畑に直まき。
人参の発芽には、光と湿り気という相反するものが必要です。
光のためには浅くまきたいが、水のためには深くまきたい。
その代わりシッカリ発芽すれば、あとは易しいです。

昨秋に種まき、冬に収穫した、大根の花

3月末の直まき大根 6週間後
4月に入りツクシがおわっても、春の畑はタンポポ、セリ、みつば、ヨモギなど、おいしいものがいっぱいです。
そして筍。
京田辺の竹林の近くではセリ、みつば、ぜんまいも採れます。
グレープフルーツ、レモンも収穫期。
甘柿・渋柿の葉が芽吹いてきます。
いつお迎えがきてもおかしくないプラムの老木も、渾身の力をふりしぼるように若葉をだしていました。

4月 実エンドウの花

5月 実エンドウの実
5月に入り、地表から姿を消していたミョウガが出てきました。
じゃがいもの土寄せ。
定植したポット苗たちも土寄せ。
落花生とトウモロコシの直まき。
そしてエンドウ類の収穫期到来です。
木津川市の畑仲間が、山わさび(ホースラディッシュ)というものをくれました。
数年かけて大きくなった桑の木たちが、木津川の畑の管理人さんちの薪になってしまい、日陰がありません。
これからぐんぐん育つミョウガの影になりそうなところに植えてみました。
落花生は悩んだすえ、どの本にも書いてないのですが、殻ごと植えてみました。
奈良の仲間うちでは、大根はサヤごと植えたりします。
大根さんは自ら種まきをするとき、サヤをはじかせて種を飛ばすので、どちらかと言えばサヤから出す方が自然に近いのかな?と思うのですが、落花生さんは触手(ランナー)を伸ばして地中に実(種)をつけます。
発芽するときは、殻の中から芽を出すのだから、その理由が養分なのか、虫からのガードなのか分からないけれど、殻つきがいいんじゃないかと思ったのです。
殻を寝かせて植えて、家に帰ってから気付きました。
殻は縦だ!
掘り返して縦に、どっちが上でどっちが下かよく見て、埋め直しました。
上下に並ぶ2つの種は、両方育つのか? 競いあって片方が負けるのか?
悩んだすえ真ん中で割って、縦方向にしたものを横に2つ並べて植えました。

3月下旬に植えたじゃがいも 6週間後
春は野菜だけでなく、お米の苗も育てなければなりません。
庭先で、発砲スチロールと、ポット苗を運ぶトレーを利用して、苗床を作りました。