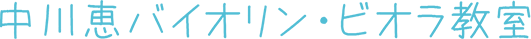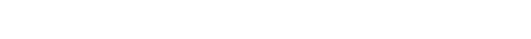バイオリン 右腕のおしごと
2022/05/03
バイオリン/ビオラを弾くときの、右腕のおしごとは何でしょう?
①腕を上げる
「腕を上げる」というおしごとは、②~④の土台となるため、大変重要です。
前鋸筋を使っている生徒さんが多く見られますが、前鋸筋を使ってはダメです。腸腰筋・広背筋・大胸筋を使い、前鋸筋・僧帽筋をゆるませます。
②弓を持つ
弓を「持つ」というおしごとは、「弾く」前に終わっています。
弓を手のなかに収める型(ポーズ)を作って、これから行う仕事に適した柔軟性を持たせれば、完了です。でも困ったことに、仕事に取り掛かるとだんだん不具合が生じてきます。
最大の悩みは、強く握ってしまうことでしょう。弾いている最中にゆるめる指示を出す必要があります。弓の折りかえしや移弦の直前にゆるめると、効果が実感しやすく、ゆるめる癖が定着しやすいです。
また型もズレてくるので、整えなおす指示を出す必要があります。私のばあい、薬指を感じなおして、薬指から他の指の位置関係を感じなおします。
よい状態が長く保てれば、脳の処理能力を使わずにすみます。その分ほかのことに脳を使えます。
右手の型や、右手への指示の出し方について、レッスンではおひとりおひとりに合った具体的な方法をアドバイスしています。
③弓を引く、おり返す
メインのおしごとです。弓を引く(こする)ことにより、バイオリンは音が出ます。
ダウンの方向と、アップの方向。動きのパターンは2つしかありません。
弦により弓の角度が異なりますから、「アップダウン ✕ 弦」で考えると全部で8パターンです。
しかしデタシェとマルトレでは動かし方が違います。ロングトーンも違います。スピッカートも違います。
さらに同じデタシェでも、弓の使う場所によって違います。デタシェもマルトレも、弓先でするのと、弓中でするのと、弓元でするのでは、右手の使い方はぜんっぜん違います。
弓を引くというおしごとのパターンは、無限にあると言えるでしょう。『右手のおしごとは何?』と問われて、『弓をアップダウンに動かすこと』と答える生徒さんが多いのも、うなづけます。
私がこのように分けて考えるようになったのは、大人の初心者の生徒さんを見ていて、「持つ」ために使う脳&筋肉と、「引く」ために使う脳&筋肉が違うことに気づいたからです。
「持つ」のがうまいのに「引く」ができない、しっかり「引く」ができるのに「持つ」が改善しない、様々なケースがあります。「持つ」と「引く」が同じ脳&筋肉を使うおしごと(能力)なら、こんな現象は起きません。
子供はまだ能力が分化していないため、「持つ」と「引く」は分かれていません。分けられません。
大人で始められた方は、別の動作なのだと理解することで、練習しやすくなることがあります。
私も4歳でバイオリンを始めたので、長年まったく意識せず練習してきましたが、「持つ」と「引く」が組み合わさっている動きと捉えるようになってから、自分や生徒へのアプローチが進化しました。
④移弦する
どの弦からどの弦へ移動するかは、E⇔A、A⇔D、D⇔G の6パターンあります。
ダウンアップか、アップダウンか。ダウンのスラー中か、アップのスラー中か。これにより6✕4=24パターン。
弓のどの場所で移弦するかや、音符の長さ(速度)によっても違います。
移弦後の次はどこへ行くのか。その弦にとどまるのか、元の弦に戻るのか、さらに違う弦へ行くのか。
③ほどではありませんが、かなり多様なパターンがあります。
「引く」と「移弦」は異なる動きです。スキルアップしたいなら、「引く」と「移弦」を切り離して練習してみましょう。「移弦」の教材と練習方法は、以下のブログにも載せています。
「移弦」とは、三次元の空間におけるどういう動きなのか。を理屈で理解することも、大人の生徒さんには有効です。それを意識してもらうための練習もあります。
なお大人の生徒さんでも、子供のように「持つ」「引く」「移弦」を分化して理解・練習するのが向かないタイプの方もおられます。そうした方を、ほかの大人さんと同じ教え方でレッスンすると、混乱させたり弾き方を悪化させたりしてしまいます。