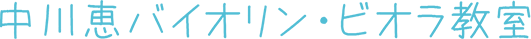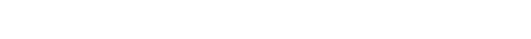メガネと眼のはなし
2020/03/19

奈良でメガネのレンズを作り直してきました。複雑な楽譜を読みながら弾かなければならないとき用です。
「複雑な楽譜を読みながら弾く」のは、主にオケです。
独奏曲は弾き込むので、あるていど暗譜状態となります。
オケでは読みながら再生(=演奏)していくので、「読み取る」ことが脳の作業として大変重要になります。また2人で1つの楽譜を見るので、眼と楽譜の距離が決まっていて、角度も斜めになります。
盛りだくさんの情報を読みながら、指揮者を見て、コンマスを見て、隣人の気配を感じ、パート全体に合わせ、他パートも聴いて、弾きます。
オケで弾き出したころは、”指揮者を見ていない” ”周りが見れてない” とよく言われました。”こんな複雑なことをしながら指揮者なんか見れるかーっ!”って思っていました。
時は流れ、今では ”指揮者を見ましょうね” と言う立場になりました。自分が辿ってきた道のりなので、具体的な練習方法やコツもわかっています。
これまでメガネは、京都でアレクサンダーテクニークを指導する深海みどり先生の紹介で、大阪江坂の「視覚情報センター」でお世話になってきました。最初は読書用と、中距離用(楽譜用と外出時)の2つを作ったのですが、かけているうちに眼球まわりの筋肉がゆるみ、どんどん視力が上がり、当時の読書用が今では外出用になりました。そこで新たな読書用と楽譜専用を作り、3つになったメガネを使い分けてきました。
しかしここ1~2年ふたたび視力が落ちてきたみたい(加齢?)で、楽譜用が見づらくなってきました。大阪江坂の予約は早くて一ヶ月待ち。奈良にあるお弟子さんのメガネ店をご紹介いただきました。

JR奈良駅から北へ10分弱「奈良オプティーク」。カフェ?美容院?を思わせる、緑いっぱいの可愛らしいエントランス。店内も木質のものが多くて落ち着きます。
初診なので状況や要望をイチから説明します。すべての検眼・測定で2時間かかりました。
田村知則先生は、イチローを始めとした超一流のスポーツ選手の眼のアドバイス、メガネ製作などをしてこられた方です。その洞察力には舌を巻くばかりですが、実のところ、悪くしてしまった眼にどう対処するかの考察・メソッドは、アレクサンダーテクニークから派生した「アイボディ」の方が腑に落ちています。
日常的にこの田村流のメガネを使うことは、腑に落ちていません。しかし現実問題として、これほど楽譜が読みやすいメガネはありません。脳みそ最小の処理能力で読めます。田村流の眼についての考え方、田村流メガネがどういうものかお知りになりたい場合は、著書をお読みください。何冊か出版されています。
「奈良オプティーク」のサイトの記事も読みやすくお勧めです。
また実際にメガネ店に行ってみたい方は、「視覚情報センター」のHPに認定店が載っています。奈良県下だと「奈良オプティーク」のほか、御所市にも認定店があるようです。
楽譜用メガネは、PCにも使っています。細かな情報が読み取りやすいです。人間がこんな作業を毎日何時間もするようになったのは、つい最近。眼球にとっても身体にとっても、負担は大きいのです。
日常生活ではあえてはずしています。田村流メガネは、視眼から細かな情報を読み取るには楽ですが、身体全体が不自然に思えるのです。ですからバイオリンの練習もレッスンも、できるだけかけずにやります。
木材をノコギリで切るのは、田村流メガネをかけていたら真っ直ぐ出来ないことがわかりました。メガネをはずしたら真っ直ぐに切れました。
「ピンホールグラス」(ピンホールメガネ)というものがあります。 「アイボディ」の理念にのっとった、眼の使い方を取り戻す訓練用のメガネです。これを使ったあとは、身体がすがすがしいです。似たような商品がネットで散見されます。
田村流メガネからピンホールグラスに変えた瞬間、後頭部から首・背中・両脇にかけての筋肉がゆるむのが分かります。それでPCのキーボードをたたいてみると、腕や指も軽やかに動きます。アイボディ流の方が身体のパフォーマンスは上がるでしょう。
しかしながら文字や音符をクリアに読むことはできないし、視界が暗くなるので使えるシチュエーションは限られます。私はテレビを見るときに使っています。
2019年秋の京田辺市役所のロビーコンサートでは、半分以上の曲をメガネなしの暗譜で演奏しました。私にとっての「試行」「挑戦」でした。今後も独奏の機会があれば、できるだけメガネなしにしたいと思います。
アイ・ボディについて知りたい場合は、本が出ています。
ピーター・グルンワルド 著 片桐ユズル 訳
誠信書房 2020年 ISBN 9784414414769
絶版となっていましたが、2回目の改訂版が出版されました。京田辺市の図書館にもあります。