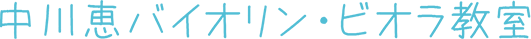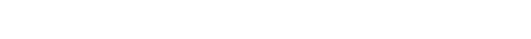ペグで調弦するか、アジャスターで調弦するか
2020/04/09

バイオリン/ビオラの調弦、ペグとアジャスターのどちらでしていますか?
かっこいいからペグでする? 楽だからアジャスターでする?
どちらを選択するかは、もっと現実的な、自分に合った理由で決めましょう。
初心者さんはアジャスターを付けましょう。ペグでの調弦は難しいからです。 バイオリン/ビオラを始めたばかりの方が、アジャスターではなくペグで調弦するのは無理です。
販売店には、お客さまのバイオリン歴を尋ねて、アジャスターの要不要を気にかける細やかさを期待したいところです。
(1) アジャスターについて
①弦とアジャスターの歴史
バイオリンという楽器が出てきたころ、弦の素材はガット(羊の腸)でした。伸び縮みが大きいガット弦は、大きく動かせるペグでの調弦が合っていました。
ガット弦の次に登場したのは、スチール弦です。ガットに比べるとスチールは殆ど伸び縮みしません。スチール弦をペグで調整するのは、恐ろしくやりにくかったのではないかと思います。
そのあとにナイロン弦が登場し、現在の主流となっています。ナイロン弦とは、ナイロンや新素材の芯材に、アルミやシルバーなどの金属を巻き付けた弦です。ナイロン弦の表面をよーく見ると、斜めにシマシマになっています。
E線だけはスチールの単線が多く、スチールの巻き線もあります。ほかの弦は温度や湿度によって音程が上下するのに、E線だけ変わりにくいのは、E線の芯材がスチールだからです。
アジャスターが何年ごろに登場したのかは、分かりません。金属加工の技術が進歩して、日常生活の中の小さな道具にも金属が気軽に使われ出したころ バイオリン弦にスチール製が登場し、それを追うように金属製アジャスターが登場したのではないか、と想像します。
②アジャスターの利点と難点
基本的にアジャスターは、無いに越したことはありません。アジャスターを付けることによる難点は、たくさんあります。
①弦の、駒に当たる位置が変わる。テールピース側の角度が変わる
②重くなる(L型だと5gほど)
③構造が複雑になり、雑音などのトラブルが起きやすい
④音質が変わる、悪くなる、木質的でなくなる
それでも
①調弦が易しい
②精神的プレッシャーが無い
③微妙な調整ができる。演奏中もできる。
という大きなメリットがあります。
調弦に時間がかかると、練習する気が失せるし、練習時間も減ります。また開放弦の音程が正確でないと、音感を育てることができず、左指を置く位置の精度も高められません。
アジャスターの形状は大きく分けて、弦1本づつに付けるタイプと、テールピース一型があります。
① L型
世の中に最初に登場したL型は、一番でん!としていて、いかにも壊れにくそう。値段も安くて、可動域が大きく動かしやすいです。
最大の欠点は、テールピース側の弦長がかなり短くなること。またネジを押し込みすぎると、バイオリンの表板を傷つける危険があります。
バイオリンのE線には、ボールエンドとループエンドがあります。L型にはボールエンドの弦を用いますが、間違ってループエンドを買ってしまっても付けられないことはないです。
バイオリン・ビオラいずれも、L型アジャスターを自分で購入するときは、弦のボールを引っ掛けるところの幅にご注意ください。「普通」と「幅広」の2タイプがあります。通常バイオリンであれば、スチール単線のE線には「普通」を、それ以外には「幅広」を用います。
アジャスターの幅は、メーカーが違えば微妙に違います。2タイプに分けていないメーカーもあります。弦の太さもいろいろなため、L型アジャスターと弦の組み合わせによっては、はまりにくいことがあります。
② ヒル型
ヒル型は、テールピース側の弦長が短いというL型の欠点を解決するタイプとして、登場しました。(と思います。) ネジの位置も、押し込みすぎてバイオリンの表板を傷つけたりしません。安価でないバイオリンにはヒル型が付いており、プロもヒル型を使います。
しかしL型にはない欠点もあります。
〇ネジの可動域が小さい。
〇鉤 (カギ) の部分で弦が切れることがある。切れることを知っている職人さんは、角の鋭さを確認し、やすりで削るなどしてからアジャスターを取り付けてくれます。その部分を改善したメーカーもあります。
〇引っ掛ける鉤が大きい(背が高い)ものは、駒からテールピース側への角度が浅くなる。鉤が小さいほど弦の角度は自然になりますが、鉤が小さいほど壊れやすいといえます。形状や材質の選択肢が多いので、なにを選んだらいいか相談できる所で買うといいでしょう。
〇機構が小さいので、壊れやすい、高い。
弦はループエンドでなければ付けられません。ラジオペンチでボールを取り除いて付けることもできますが、ボールはかなり外れにくいです。
ボールエンド/ループエンド両用という弦もあって、これはボールが外しやすくなっているようです。
③ 分数バイオリン用
弦のテールピース側をはずさないと付けられないL型/ヒル型と違い、弦をゆるめるだけで取り付けられます。が、フルサイズの楽器には向きません。楽器に比べてアジャスターが小さすぎるのです。(フルサイズ用の、この形状のアジャスターがあってもいいと思うのだが。)
弦をはさむ隙間の幅も2種類あって、E線には「普通」、ADG線には「幅広」を使います。
ネジの可動域も小さく、押し込むほどに硬くて動かなくなりますが、単純な形状で安いです。
④ テールピース一体型
テールピースとアジャスターが、プラスチックの一体成型になっており、全ての弦をはずしてテールピースごと交換します。テールピースを外すと一旦エンドピンがゆるみ、取りつけるテールガットの長さ調節もいりますから、工房で交換してもらうのがベストです。
構造を理解していて、工作が得意な人は、自己責任で交換することもできます。「2020/10/28 アジャスター付きテールピースへの交換」の記事を読んで判断してください。
4弦全部にアジャスターを付けるなら、一体型がお勧めです。余計な部品のないスマートさ、ネジの回しやすさ・可動域など。材質がプラスチックなことによる壊れやすさや、音質への影響など短所はありますが、メリットの方が大きいと思います。
テールピース部分が木製のタイプもあります。こちらの方が響きはいいでしょう。見た目もいいです。アジャスターはプラスチックですが、一体成型のものと違ってネジの可動域が少ないです。
調弦できるペグとは
(a) ペグと穴がぴったり吸いついている
(b) ペグソープが塗ってある
(c) 回すのに力がかけやすい向きになっている
①楽器を引きわたす時にされるべきこと
専門の楽器店や工房では、仕入れた楽器のペグが未調整であれば、お客さんに引きわたす前に調整をします。
利益の少ないセットバイオリンでアジャスターが付いている場合は調整しませんが、数十万円以上の価格帯の楽器であれば、ペグは調整して販売するのが普通です。
私が長年お世話になった大阪の職人さんは、取り扱うすべてのバイオリン/ビオラ/チェロで (a) (b) (c) をしていました。
ペグが動かずアジャスターも付いていないバイオリンを見かけることは、そう珍しくありません。様々な楽器をあつかう楽器店の店頭にも並んでいますし、バイオリン教室に持ち込まれる安く買ったバイオリンの殆どがそうです。
自分の楽器の、ペグの先端を見てみましょう。
穴の際までペグが入っていますか?
穴の際までペグが届いていなかったり、穴から先端が出すぎているのは、ペグと穴が十分に吸いついていない恐れがあります。
ペグとペグ穴は摩擦で止まっており、接している面積が広いと安定します。しかし調弦のため動かしているうちに歪んできて、接触面積が少なくなってゆきます。
昔のセットバイオリンはペグが調整されていませんでした。ペグを滑らかにしたければ、購入者がペグソープを塗ったり、販売店がペグを削ったりしていました。
しかし近年のセットバイオリンは、メーカー出荷時にペグ調整がされているものが増えてきました。ペグの知識がない購入者・販売店でも取り扱えるよう、多様なチャンネルで売りたいグローバル企業の戦略でしょうか。
アジャスターも昔は、販売店や購入者が金属アジャスターを後付けしていたのですが、最初からウィットナー社の一体型が付いているものが多くなってきました。
弦もドミナントが張ってあるものが目立ってきました。分数バイオリンは使いまわされることが多いので、これまで安くて切れにくいスチール弦が張られてきました。しかしドミナントだと それだけでバイオリンの鳴りが良くなり、楽器が上等そうに見えます。
②自分でできること
バイオリン/ビオラを買ったあとは、ペグソープは自分で塗らねばなりません。弦を交換するとき、予防的に塗る癖をつけましょう。
ペグは調弦で動かしていると、だんだん滑りが悪くなってきます。ペグが回りにくくなってから塗ろうとすると、一旦弦を外して、再び張らなければなりません。一度ペグに巻き付けた弦は、先端にクセがついて、新品よりかなり張りにくくなります。
ペグソープの塗り方
2020/09/08 バイオリン・ビオラ 弦の交換方法
ペグの角度も、「ペグ調弦をするとき力の加減がしやすい向き」にしましょう。ナイロン弦は張ってから1週間で1/4周くらい伸びます。ですので、弦が伸びたあと丁度よいペグの角度となるよう調整しましょう。
ペグの角度がよければ、アマオケの一斉チューニングでペグ調弦するのも恐くありません。恐いから動かさない、押したり引っぱったりしてごまかす、それではいい音程での演奏ができません。
①バイオリン
バイオリンのE線にはほぼ必ずアジャスターが付いています。弦の張りが強く、ペグでの微調整が難しいからです。
ADG線に一流の演奏家がアジャスターを付けることは滅多にありませんが、皆無ではありません。
分数バイオリンは、EAの2本に付いているのを見かけます。E線の次にテンションが高いこと、またA線は出番が多いから、などが理由と思います。
②ビオラ
ビオラも第1弦のA線にアジャスターが付いています。なぜかL型しかありません。
L型アジャスターを付けると、弦の駒に当たる位置がかなり変わってしまいます。弦はかなり厳密に設計・開発されており、駒やナットに当たる位置が2cmずれるのは、相当な狂いだと思います。
ヒル型でビオラに付けれるものがあればいいのに、と思うのですが見当たりません。ヒル型が登場しないのは、ループエンドの弦がないから、でもあるのでしょう。
バイオリンに比べるとビオラは大きくて重たくてベグボックスも遠いので、その分ペグでの調弦はしにくいです。そのためか、A線以外にもアジャスターを付けている演奏家を、バイオリンより見かけます。また弦のテンションの低さからか、A線にアジャスターを付けないこともあるようです。