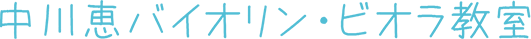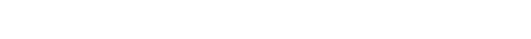立って弾くのが良いとは限らない
2019/08/24

私は偏平足・開帳足です。
立ったとき、大地にしっかり反発して立つことができません。無意識にかかとへ重心をやってしまいます。
バイオリンを弾くときも、重力・反重力の双方向へエネルギーをうまく流せず、そのため胸郭を左右へのびやかに開くことができません。
椅子に腰かけると、座骨が「足」がわりとなります。ゆえに立っている時とは、違った体幹を構築できます。
現代人は偏平足・開帳足が多い。足や脚に課題があるばあい、座った方が上手に弾けたり、楽に弾ける身体感覚をつかめるのではないか。ということでバイオリン教室では「座って弾く」ということをレッスンで取り入れています。
家での練習にも取り入れてみてください。浅めに腰かけて、骨盤を立てましょう。
レッスンでは、立ったり座ったりしながら弾くこともします。あまり難しい演奏はできません。解放弦のロングトーンなどをします。
この立ったり座ったりというのは、アレクサンダーテクニークの基本動作です。ただ立ったり座ったりするだけの練習をバイオリンのレッスンに取り入れるのは難しいのですが、自分自身はよくやります。

跪座(きざ)の姿勢でバイオリンを弾くのも、良くやります。跪座とはしゃがんだ姿勢で、膝を床について、かかとにお尻を乗せます。
スクワットもやります。(バイオリンを持って)
綱引きもやります。(バイオリンを置いて)
これらは子供に良く取り入れるのですが、後ろで保護者さんが目を白黒させています。だんだん何のレッスンか分からなくなってきますが、身体が動かなければバイオリンは弾けないのです。
”身体が動くようにしてからバイオリンのレッスンに連れてきてください” と言いたいところですが、バイオリンのために動く身体作りを頑張る、という順番も悪くないと思っています。
”筋トレをすればいいのですか?”
と良く聞かれますが違います。
”ストレッチ?”
違います。
鬼ごっこ、木登り、雑巾を使った掃除、和式トイレ、などをしてください。
一番レッスンに取り入れてみたい動きは、腰割りの姿勢から歩くこと(腰割りとは、お相撲さんが四股(しこ)を踏むときの姿勢)ですが、まだしたことはありません。
大学の演劇部にいたときに、していました。
尻打ち、ルコックなど、日本的な身体の使い方・修練から取り入れた基礎練が多かったです。

足裏の話に戻ります。
この自分の足・脚で、どうしたらハイパフォーマンスな演奏が出来るか?というのは大きな課題でした。
様々なメソッド・身体操作法を探しましたが、一番腑に落ちているのが水口慶高さんという方のメソッドです。
「足についての本当の知識」 水口慶高 実業之日本社
もっと新しい著書もありますが、これが分かりやすい。偏平足(外反母趾)の原因は、脚の過剰回内が原因との説です。単に「偏平足で困っている」という方にもすごく役立つ本です。
脚の過剰回内を正すには、膝を「外側」且つ「上側」へ向けるよう意識すべし、とあります。これが実践してみるとなかなか良いのです。
何人かの生徒さんにも試したことがあるのですが、劇的に変わった方もおられました。身体の使い方で弾きやすさが違ってくる、ということをリアルに理解したようです。