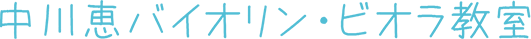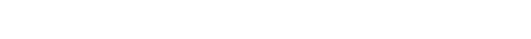弦や顎当てが長持ちする、バイオリンの拭き方
2022/09/22
バイオリン・ビオラを弾いたあとは、しまう前に布で拭きましょう。拭き方で、弦や顎当ての寿命が違ってきます。バイオリン・ビオラ本体も良いコンディションが保て、結果として余計な出費が防げます。
汚れは大きくわけて2種類あります。松脂と皮脂です。汚れの種類が違うので、布は2枚要ります。
弾いた直後なら、汚れは取れやすいです。時間が経過すると、取れにくくなります。拭かないまま次の練習をすると、汚れが溜まってゆきます。ですから、バイオリンを取り出したとき必ず松脂を塗るのと同じで、バイオリンをしまうときのルーティンにしましょう。
ピアノと比べると、バイオリン・ビオラは準備&片付けに時間のかかる楽器です。しかし、組み立て&分解が必要な管楽器に比べると実は早いんですよ。アマオケに入るとわかります。
拭いたときのメリットが分かっていても、それが面倒で練習しなくなってしまうのは本末転倒です。ですから、どこまで丁寧に拭くかは各自決めてください。性格や生活習慣は人それぞれです。
子供の生徒の楽器を見て、あんまり拭いてないな~と思っても、先生はうるさいことは言いません。
バイオリン・ビオラを習い始めるときに、拭き方の説明は必ずしています。しかし習い始めたときにしか言わないので、習い始めたときは沢山のことを憶えなければならないので、え?そんなこと教えてもらったっけ?という方、おざなりになっている自覚がある方は、この記事で復習しましょう。
(1)布の素材
(2)皮脂の拭き方
(3)弦についた松脂の拭き方
(4)弦以外のところにつく松脂
(1)布の素材
「きめが細かく」「柔らかく」「けば立たない」綿がベストです。昔ながらのハンカチ、手ぬぐいなど。リネンもいいでしょう。
バイオリンを買うと、マイクロファイバークロスがもらえることがあります。メガネを拭くときに使う、アレですが、使い方には少し注意が必要です。
布はときどき洗いましょう。私は1~2週間ごとに洗います。

(2)皮脂の拭き方
一番汚れやすいのは、顎当て&テールピースの上部と側面です。
皮膚が触っているところに皮脂がつき、これらを放置すると、数日~数週間で垢が溜まっているのが目に見えるようになります。
側面は、拭かずにいると、顎当ての金具がだんだん曇ってきます。数カ月~数年で青カビ(緑青)が発生し、顎当ての交換が必要になることもあります。
金具についた汗を放置すると、金属アレルギーも発症しやすくなります。金属アレルギーは花粉症と一緒で、なんともなかった人が突然なります。金属アレルギーの人向けに、プラスチック製の顎当てや、顎当てカバーが発売されています。それくらい、金属アレルギーのバイオリン弾きが一定数いるということです。
首や顎のほかに、バイオリンと皮膚が触れるのは、左手です。指板の上、親指をはわせるネック、ポジションを使うばあいはヒールや本体の肩のあたりも触ります。
指の腹に汗をかいたら、必ず指板の上も拭きましょう。駒のあたりから弦と指板のあいだに布を入れて、上へスライドさせます。
皮脂がつく場所の材質は、
①顎当て・テールピース・指板(黒檀やローズウッドなど硬めの木、染み込むタイプのニス)
②顎当ての脚(金属)
③ネック・ヒール(メイプル、染み込むタイプのニス)
④バイオリン・ビオラ本体の肩(表面を覆うタイプのニス、メイプルとスプルース)
と多様です。金属部分とバイオリン本体では、材質の傷つきやすさがかなり違います。
バイオリン本体は、強い素材でゴシゴシ拭いてはいけません。ニスが削れてしまいます。マイクロファイバークロスなどを使うばあいは、やさしく拭きましょう。
そもそもバイオリン・ビオラの本体を拭くのに、マイクロファイバークロスはお勧めではありません。何故バイオリンを買うと、マイクロファイバークロスが付いてきたりするのでしょうか。まるでそれで拭けと言わんばかりです。管楽器のために始まったサービスが、そのまま弦楽器に為されているのでしょうか。
マイクロファイバークロスで拭いていい箇所もありますが、①~④などの場所ごとに、布や、拭く強さを変えるのは現実的ではありません。私はハンカチで拭いています。「きめが細かく」「柔らかく」「けば立たない」布がいいです。
取りはずしてストックしてある顎当てにも、青かびを発見することがあります。垢が残っていたのでしょう。ひどくなると金属と木の接点がぐらぐらになって、どちらのパーツも使えなくなります。しばらく使わないフィッティングパーツは、しまう前に丁寧に拭きましょう。
(左)プラスチックの顎当て (右)顎当てカバー
分数バイオリン用を多く揃えています。
(3)弦についた松脂の拭き方
松脂が一番付着するのは、弦です。松脂がつきすぎた弦は、弾きにくくなります。しまう前に必ず拭きましょう。練習の途中で拭くこともあります。
弦についた松脂を拭かずにいると、時間とともに硬質化し、分厚くなってゆき、弦の劣化が早く進みます。音質が悪くなり、弾きにくいため、余計な力を入れて弾くようになります。
松脂はねとねとしています。柔らかい布で拭くときは、少し強めに押し当てましょう。キーキーと音が立つ手前くらいの強さで拭きます。
新品の弦を強めに拭くと、布に黒い汚れがつくことがあります。これは「取りすぎ」だと思います。弦から油分をうばい、弦の表面を削っているのではないかと思います。松脂は研磨剤でもあるのです。
最初の数回はやさしく、布に黒い汚れがつかない程度に拭いて、弦がちょっぴりくすんできたら、強く拭きましょう。マイクロファイバークロスは、くすんできた弦にはいいですが、新品の弦を拭くのには向きません。
弦に付着した松脂はたいへん取れにくく、巻き線のミゾに入り込んでゆきます。練習後に毎回拭いていても日々劣化を感じ、数週間後には交換したくなります。なんとか弦を長持ちさせたくて、いろんな拭きとり方法を試してきました。
①専用のクリーナー
それなりの値段するのに全く効果を感じられません。それどころか溶剤が弦に染み込んでいく様子が、かえって弦に悪いような気がしてきました。(気がしただけです。確証はありません。)
②アルコール
何度かやってみた実感としては、その時は松脂が取れて気分が良くても、その後に弦が傷みやすい気がします。専用クリーナーと同じで、なにやら弦に染み込んでいくのが気がかりです。Warchal社という弦メーカーからも「アルコールで拭くことを推奨しない、かえって弦を痛める」との見解が出ています。
③皮の布
化学的手法ではなく、物理的手法で取れないか?と考えました。おそらく管楽器用ですが、楽器を拭くための皮が売られています。皮は対象物に吸いつき、強く拭けるのですが、弦の表面がガサガサして荒れてきて、長持ちしません。
④紙ヤスリ
あまり大きな声では言えませんが、紙ヤスリで削っていたこともあります。松脂がこびりついてゴワゴワがひどくなってきた時に、1~2週間でいいから長持ちさせて、弦代を節約するためです。
普段通りに拭いたあと、硬質化しているところをやさしく削ります。紙ヤスリ/布ヤスリは、目の粗さが「番手」という数字で表されます。家にあった #400 を使いましたが、もっと細かい方が弦を痛めにくいと思います。
硬質化した松脂を薄くするていどに使い、弦そのものにまで到達しないようご注意ください。

(4)弦以外のところにつく松脂
松脂は、バイオリンの表板や弓の棹にも飛びます。弓の毛にぬる松脂が多すぎると、弾きにくいばかりか、バイオリン本体の表板や、弓のスティックもまっ白になります。
どちらも拭くばあいは、表面のニスを傷つけないようにしなければなりません。しかし松脂はニスとの親和性が高く、ねとねとしているので、飛び散った松脂を取りきることはできません。松脂はニスの材料でもあるのです。
一番の対策は、弓の毛に松脂を塗りすぎないことです。
あるとき松脂を塗りすぎてしまう子がいました。練習後もバイオリンを拭きませんでした。松脂の適量をおぼえるより、バイオリンを拭くより、せっかく買ったバイオリンを弾いてもらうことの方が大事なので、ちょこちょこ指摘しながらも うるさく言わないでいました。
ある日レッスンに来たら、表板のニスと松脂が溶けあって固まっていました。夏でしたから、暑いところに一定時間 置いていたのでしょう。
余談ですが、安物のバイオリンは、樹脂をアルコールで溶いてスプレーで塗ります。
本来のバイオリン製作では、オイルに松脂など複数の天然素材を溶かし、人の手で塗っては乾かすということを何週間もかけて繰り返します。
樹脂スプレーのバイオリンは音色が悪く、木材への親和性や粘りもないため剝がれやすく、バイオリンを守るという保護効果も劣ります。
黒猫ダークの松脂を、お餅のように変形させた子もいました。本人は首を横にブンブン振っていましたが、おそらく車内への置き去りでしょう。。