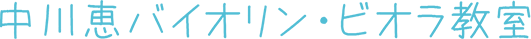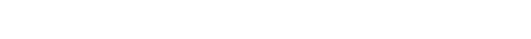ペグがゆるむ現象への対策
2021/01/10

暖かな日もあれば、突然ぐっと冷え込んだり。寒暖の差は楽器にとってもよくありません。このところペグ(糸巻き)が戻る生徒さんが続出したので、記事にまとめてみました。
ペグが戻りやすいのは、
(1)持ち主の取り扱いが適切でない
(2)売り主の調整が適切でない
などが原因です。
(1)持ち主が気づかうべきこと
①ペグソープを塗るべし
ペグには必ず、ペグソープ(ペグコンポジション)を塗りましょう。基本の「キ」です。
弦を取り外して塗りなおすのは、手間がかかります。
ペグで調弦をしている方は、弦を交換するとき必ず塗りましょう。
ペグが回りにくい or 止まりにくいという不具合に対し、良心的なスタッフ・職人さんなら、まずペグソープを塗り、様子を見るよう言ってくれます。よほどペグとペグ穴が合っていない楽器でなければ、改善されます。
ペグソープで不具合が解消できなければ、ペグとペグ穴を削ります。
正規の工賃は安くはありません。しかし買ったところに持ちこめば、安く仕上げてくれるはずです。それなりの価格帯の楽器で、且つ 買ったばかりであれば、引き渡し前の調整不足です。
京都市内の楽器店で、生徒が50万円ほどの楽器を衝動買いしてきたことがありました。
楽器そのものは良いようでしたが、アジャスターが付いていないにもかかわらず、ペグがぱきぱきいってスムーズに回りません。調弦できない商品を販売するのはおかしい、と生徒に伝えると、再度お店へ足を運んだようです。営業さんがペグソープを塗ってくれたとのこと。(職人さんはいないお店です。)
こちらの記事にペグソープの塗り方のほか、弦を交換するときに した方がよいことを書いています。
②ペグは押し込みながら回すべし
調弦でペグを回すときは、押し込みながら回しましょう。
ペグは先端が細く、根元が太くなっているので、普通に回していると穴から抜ける方向へ動いてゆきます。押し込みながら回していても徐々に浮いてきます。
大事な本番前は、正面にかかえて両手でペグを押し込んでおきましょう。ゆるみやすくなっていないペグでも、1mm程のめり込んだりします。
以下の記事も参考になさってください。
2020.04.30 バイオリン・ビオラの調弦方法 (2)ペグでのやり方
③気温・湿度の変化がないようにすべし
楽器や弦は、思っている以上に、温度・湿度の変化に敏感です。赤ちゃんと同じと考えましょう。冬や夏、車のなかに置き去りにはしてはダメです。家の中でも、冷える場所、日光があたる場所、冷暖房があたる場所などは避けてください。
ペグがしょっちゅう戻ったり、新品の弦が切れたりする生徒さんがおられました。
弦の交換は信頼できる職人さんがしていて、駒に鉛筆芯の跡などもあり、見たところ問題なし。ペグも私がしっかり押し込んでいる。車に置き去りもしていないなら、あと考えられるのは室温の変化だけなんだけど・・というお話をしたら、置く場所の見直しをしたようで、ペグは戻らなくなりました。
戻る現象が起きていたころは、弦の駒にあたっているところの、巻きの幅が広がって見えていましたが、それもなくなりました。
生徒さんが ”暑いところには置いていません” と言っていても、ニスが溶けていることがあります。松脂が溶けたこともありました。
ペグが戻る現象も、”温度・湿度の変化するところには置いていません” と生徒さんが言っても、頻繁に戻る現象が改善されないことがあります。しかし置く場所、保管のしかたを変えてもらうと、必ず止まります。
バイオリンは、ほんの少しの暑い寒いや、湿気や乾燥に影響されるのです。
●電子チューナーは、微細な音程の調整につかう道具で、音程が大きく下がったときは役にたちません。
そのためペグの緩みにより音程が大きく狂ったばあい、どの程度ペグを巻き戻したらいいか分からなくなることがあります。
そうした場合のお助け道具として、調子笛(ピッチパイプ)というものがあります。4管だけのハーモニカのような器具で、バイオリン4弦の音がピンポイントで鳴ります。これを吹きながらペグを巻き上げていくと、弦を張りすぎてしまうことがなく安心です。
Hzが何種類かあります。442Hzのものを買ってください。
ピアノなど鍵盤楽器があれば、それを使ってもいいでしょう。
(2)売る側がしておくべき調整
こちらに少し書いています。詳しくはまたの機会に。